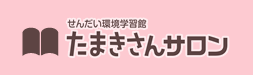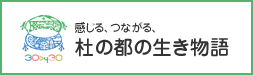サロン講座
「手漉き和紙ワークショップ〜和紙を学ぶ〜」を開催しました 
投稿日:2025年02月14日(金)
このイベントは終了しました。
たまきさんサロンスタッフです。
講師に手すき和紙工房 潮紙 代表 塚原英男さんに登壇いただき、2月9日(日)にサロン講座「手漉き和紙ワークショップ〜和紙を学ぶ〜」を開催しました。
手漉き和紙の技術や歴史、 和紙の特性などについて教えていただき、アカネで色付けした和紙を漉き、素材から仕立てまでのモノづくりの体験講座でした。
講座の準備で、塚原さんが手すき和紙の行程の「黒皮むき」をしている中、続々と周りに集まり体験会と講話が始まり、参加者の皆さんの関心の高さが伺えました。

塚原さんは宮城県に400年伝わる柳生和紙工房で8年間修行され、その後仙台市内の福祉作業所で和紙作りを教えていらっしゃいました。
震災後の2014年に ご自身の工房『手すき和紙工房 潮紙』を川崎町に立ち上げ、和紙を通して先人の智慧を後世に伝える活動をされています。
手すき和紙技術は2014年にユネスコの無形文化遺産に指定されました。
1300年前にコウゾで作られた和紙が奈良県の正倉院に保管されているそうです。
1700年前に中国から伝えられた時の紙は麻や綿が使われていました。強度も弱く、厚みがあり、肌が粗い紙だったそうで、鹿の角やイノシシの牙で磨いて表面を滑らかにしていたのだそうです。
すでに、日本では南洋諸島から伝わっていたコウゾを使った布を仕立てていたので、その後、日本独自の工夫を取り入れ和紙へと発展していったのではないかとのことでした。

手漉き和紙ができるまでの行程は、「コウゾの刈り取り→蒸かし→皮むき→黒皮むき→煮熟(不純物を取り除く作業)→塵取り(細かい塵(ちり)を取り除く作業)→叩解(繊維をたたいて細かくほぐす作業)→紙すき→圧搾(水を搾りだす作業)→乾燥)」です。
手すき和紙は植物繊維のセルロースを使っているため、なかなか破けず丈夫で長持ちです。

「黒皮むき」の行程では削ることでセルロースを出していて、これを「白皮」と呼んでいるそうです。
和紙は、本来 木の皮の色をしています。

また、道具の「すだれ」について、竹の節にあたる部分のつなぎ目は接着されていません。糸の強さで密着させているのだそうです。
そして、日本で作れるのは現在3人しかいません。
また、この竹ひごを作れる方がもういないのだそうです。
日本の技術が危ぶまれる状態であることも教えてもらいました。

さて、紙すき作業です。

アカネ(つる性多年生植物)の根で色付けをした楮と水とトロロアオイを使います。

前後左右に動かすことにより繊維に方向性が生まれ、なめらかで美しい紙になります。



春のようなあたたかい素敵な色の手漉き和紙が出来上がりました。
乾燥させれば出来上がりです。

「植物を紙にする」和紙とは自然と共に過ごしていた先人たちの知恵でした。多くの行程があり、手間を掛け、丁寧な作業が必要であること、代表的な和紙の材料のコウゾやミツマタ、ガンビ等のほとんどが国外で育てられ「黒皮むき」の行程までされている現状、道具などの技術の後継者の現状、技術や品質が優れていても「和紙作り」それだけでは成り立たなく、職業としての和紙職人の環境が厳しい事も、手すき和紙の伝統を守っていく大切さも知ることができました。
塚原さん、ご参加頂いたみなさま、ありがとうございました。
こちらもご覧ください。
たまきさんサロン サロン講座
たまきさんサロン
‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*
せんだい環境学習館たまきさんサロン
平 日 10:00〜20:30
土日祝 10:00〜17:00
休館日 月曜(月曜が休日の場合は、その翌日)休日の翌日・年末年始
*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*
講師に手すき和紙工房 潮紙 代表 塚原英男さんに登壇いただき、2月9日(日)にサロン講座「手漉き和紙ワークショップ〜和紙を学ぶ〜」を開催しました。
手漉き和紙の技術や歴史、 和紙の特性などについて教えていただき、アカネで色付けした和紙を漉き、素材から仕立てまでのモノづくりの体験講座でした。
講座の準備で、塚原さんが手すき和紙の行程の「黒皮むき」をしている中、続々と周りに集まり体験会と講話が始まり、参加者の皆さんの関心の高さが伺えました。

塚原さんは宮城県に400年伝わる柳生和紙工房で8年間修行され、その後仙台市内の福祉作業所で和紙作りを教えていらっしゃいました。
震災後の2014年に ご自身の工房『手すき和紙工房 潮紙』を川崎町に立ち上げ、和紙を通して先人の智慧を後世に伝える活動をされています。
手すき和紙技術は2014年にユネスコの無形文化遺産に指定されました。
1300年前にコウゾで作られた和紙が奈良県の正倉院に保管されているそうです。
1700年前に中国から伝えられた時の紙は麻や綿が使われていました。強度も弱く、厚みがあり、肌が粗い紙だったそうで、鹿の角やイノシシの牙で磨いて表面を滑らかにしていたのだそうです。
すでに、日本では南洋諸島から伝わっていたコウゾを使った布を仕立てていたので、その後、日本独自の工夫を取り入れ和紙へと発展していったのではないかとのことでした。

手漉き和紙ができるまでの行程は、「コウゾの刈り取り→蒸かし→皮むき→黒皮むき→煮熟(不純物を取り除く作業)→塵取り(細かい塵(ちり)を取り除く作業)→叩解(繊維をたたいて細かくほぐす作業)→紙すき→圧搾(水を搾りだす作業)→乾燥)」です。
手すき和紙は植物繊維のセルロースを使っているため、なかなか破けず丈夫で長持ちです。

「黒皮むき」の行程では削ることでセルロースを出していて、これを「白皮」と呼んでいるそうです。
和紙は、本来 木の皮の色をしています。

また、道具の「すだれ」について、竹の節にあたる部分のつなぎ目は接着されていません。糸の強さで密着させているのだそうです。
そして、日本で作れるのは現在3人しかいません。
また、この竹ひごを作れる方がもういないのだそうです。
日本の技術が危ぶまれる状態であることも教えてもらいました。

さて、紙すき作業です。

アカネ(つる性多年生植物)の根で色付けをした楮と水とトロロアオイを使います。

前後左右に動かすことにより繊維に方向性が生まれ、なめらかで美しい紙になります。



春のようなあたたかい素敵な色の手漉き和紙が出来上がりました。
乾燥させれば出来上がりです。

「植物を紙にする」和紙とは自然と共に過ごしていた先人たちの知恵でした。多くの行程があり、手間を掛け、丁寧な作業が必要であること、代表的な和紙の材料のコウゾやミツマタ、ガンビ等のほとんどが国外で育てられ「黒皮むき」の行程までされている現状、道具などの技術の後継者の現状、技術や品質が優れていても「和紙作り」それだけでは成り立たなく、職業としての和紙職人の環境が厳しい事も、手すき和紙の伝統を守っていく大切さも知ることができました。
塚原さん、ご参加頂いたみなさま、ありがとうございました。
こちらもご覧ください。
たまきさんサロン サロン講座
たまきさんサロン
‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*
せんだい環境学習館たまきさんサロン
平 日 10:00〜20:30
土日祝 10:00〜17:00
休館日 月曜(月曜が休日の場合は、その翌日)休日の翌日・年末年始
*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*